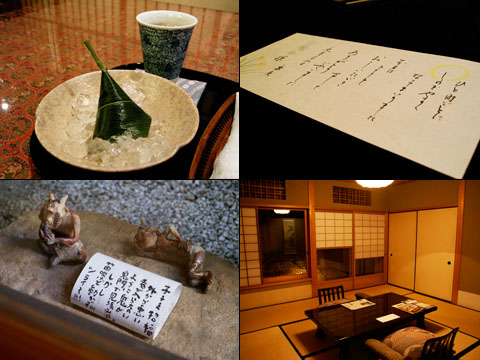ふじおか@黒姫

はてさて…この店について一体どう書いていいものか…。単純に「人生で一番衝撃的な蕎麦屋」とだけ書いて終わりにしたいところだが、それでは書いた事にならない。この戸惑いは様々な言葉に出来ない理由によるが、まず言える事は、ここまで蕎麦という素材を研ぎすましてしまうと、最早蕎麦と呼んでいいものかどうか分からなくなる、ということだw。勿論これ以上無い賞賛の意味で言っている。見た目、香り、腰、喉越し、歯応え、味、どれをとっても鮮烈過ぎて最早これまでの(決して多くない)経験値を総動員しても判別不能なくらい別の価値を持ってしまっている。何か科学的な方法や、もしかすると呪術めいた手法まで用いて強制的に純度を上げたのではないかと妄想してしまうくらい、『蕎麦過ぎて』頭がクラクラしてくる。仮にこれを蕎麦とした場合、これまで俺が食ってきた『蕎麦と呼ばれるもの』の9割以上は蕎麦ではない、ということになってしまう。少なく見積もってもそれくらいの差はあるのだ。
もともと蕎麦食というのは、他の料理以上に求道者を虜にする何かがある食文化だと思うが、本当に極めてしまうと、その価値体系をも突き破って、そのテリトリーにいる人間には判別不能なものになってしまうのだという事が思い知らされる。したがって、この店を基準に今後の蕎麦食を楽しもうったってそうはいかない。今後この店を越える蕎麦を食べる事は叶わないだろうと思うと、「ああ、(少なくとも今)食うんじゃなかった…」という気持ちの方が強いのが正直な感想である。そうなのだ、蕎麦という料理を「突き詰めた」という意味において、この店以上の店は恐らく無い。それは食の満足度とは別の話だ。この店に心底尊敬と畏怖の念を抱くと同時に、全く、とんでもなく厄介な店に行ってしまったものだという気持ちが未だ心から離れない…。
名前自体は、その評判も含めてもう随分前から知っていた。しかしこれまで行く事が無かったのは、勿論その悪過ぎる立地や、完全予約制で昼の一回転のみ、という食う以前のハードルの高さもあるが、美味こそ何よりも優先される俺にとっては、それ程大きな障害にはならない。恐らく上記のような事態を予見した俺の第六感が拒否していたのだろう。この店は危険だとw。そしてそのアラートが示す危険度は全く正確であったと。これより先の文章はなるべく完結に記すよう心がける。そこには『この感動は、俺の筆力で書いてもどうせ伝わらない』という諦観がある事はあらかじめ正直に記しておく。